最新情報 一覧
-
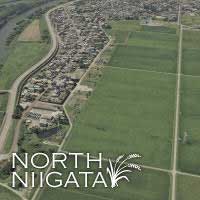 2024.04.24ゴールデンウィーク期間中の施設営業について
2024.04.24ゴールデンウィーク期間中の施設営業についてお知らせ
-
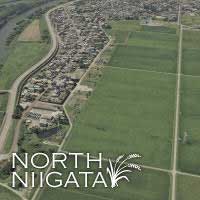 2024.04.24金融共済部からのお知らせ日頃、JA事業にご愛顧賜り誠にありがとうございます。 ゴール[…続きを読む]
2024.04.24金融共済部からのお知らせ日頃、JA事業にご愛顧賜り誠にありがとうございます。 ゴール[…続きを読む]JAバンク
-
 2024.04.17チューリップ花摘み体験JA荒川支店は4月16、支店共同活動として村上市荒川地区の保[…続きを読む]
2024.04.17チューリップ花摘み体験JA荒川支店は4月16、支店共同活動として村上市荒川地区の保[…続きを読む]トピックス
-
 2024.04.17乾田直播実演研修会 管内生産者ら50人が参加 JA北新潟は4月13日、全農にいがたとヤンマーアグリジャパ[…続きを読む]
2024.04.17乾田直播実演研修会 管内生産者ら50人が参加 JA北新潟は4月13日、全農にいがたとヤンマーアグリジャパ[…続きを読む]トピックス
-
 2024.04.12令和6年4月 会長あいさつ 3月1日、JA北新潟が発足しました。この合併に至るまで、多[…続きを読む]
2024.04.12令和6年4月 会長あいさつ 3月1日、JA北新潟が発足しました。この合併に至るまで、多[…続きを読む]会長メッセージ
-
 2024.04.12【テレビ放送お知らせ】管内の越後姫生産者がテレビに出演しますBSN新潟放送の週刊県政ナビに管内の越後姫生産者が出演します[…続きを読む]
2024.04.12【テレビ放送お知らせ】管内の越後姫生産者がテレビに出演しますBSN新潟放送の週刊県政ナビに管内の越後姫生産者が出演します[…続きを読む]お知らせ
-
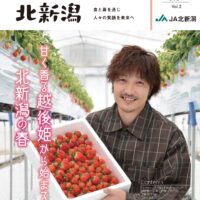 2024.04.12広報「manma!北新潟」 4月号を発行しました!
2024.04.12広報「manma!北新潟」 4月号を発行しました!トピックス
-
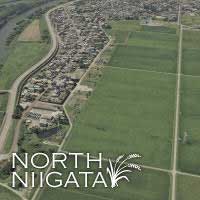 2024.04.11JA北新潟 住宅ローン とくとくプラン
2024.04.11JA北新潟 住宅ローン とくとくプランJAバンク
-
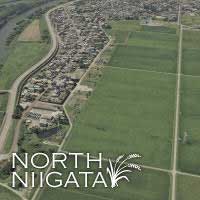 2024.04.11JA北新潟 リフォームローン とくとくプラン
2024.04.11JA北新潟 リフォームローン とくとくプランJAバンク
-
 2024.04.08越後姫の魅力 売り場から発信 読売ジャイアンツ球場でPR 3月30日、31日、読売ジャイアンツ球場(神奈川県川崎市)[…続きを読む]
2024.04.08越後姫の魅力 売り場から発信 読売ジャイアンツ球場でPR 3月30日、31日、読売ジャイアンツ球場(神奈川県川崎市)[…続きを読む]トピックス
